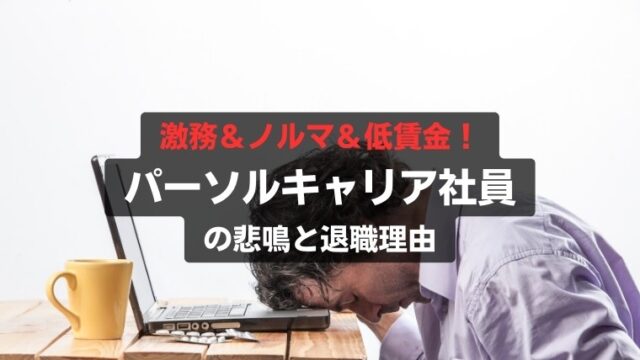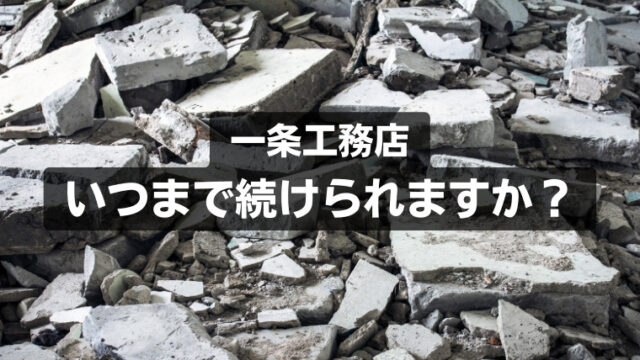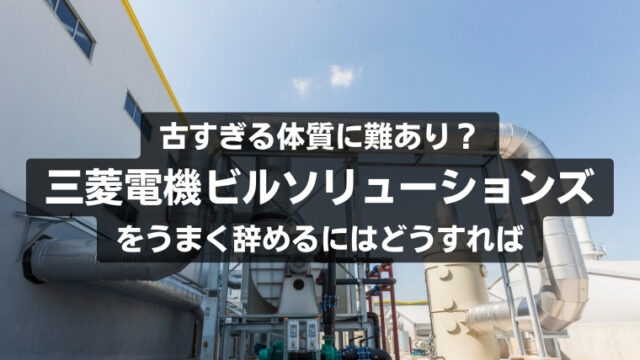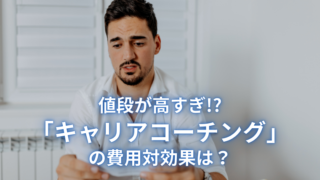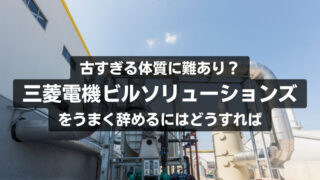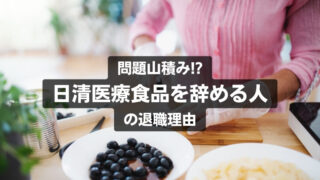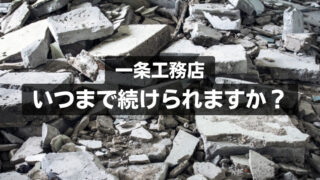本来、仕事を指導し、積極的に他部署と連携を取り、仕事を円滑に進めるための整備を行うはずの上司が仕事をしない、何もしていないと感じた場合、イライラするのは当たり前の話です。
インターネットで語られる「仕事をしないおじさん」「職場で何もしない上司」は、どれほど存在するのでしょうか。
本記事では「仕事をしない上司」に焦点を当て、その「発生するメカニズム」「一緒に働くコツ」「ボスマネジメント」について紹介します。
キャリアアップの強力サポート!
「非公開求人」多数のエージェントにまずは登録
何もしない上司は多くの職場で存在する
結論からお話をすると、仕事をしない上司は多くの職場で存在します。
厄介なことに、部下の努力で改善させるのは難しく、仕事をしない上司に遭遇してしまったら「運が悪い」としか言いようがないこともあります。
特に新卒や転職したばかりの人は、新しい環境で仕事が始まり、モチベーションが高い状態かと思います。そんななか上司が仕事をせず、やる気を感じられない状態だとモチベーションを削がれてしまい、日々の業務に影響が出てきます。
また、正そうと思っても、会社に入ったばかりの状態だと指摘するのは難しいでしょう。上司のやる気があろうとなかろうと、部下は与えられた仕事をしっかりこなしていくしかありません。
記事後半ではこのような上司をコントロールするコツを解説していきますが、まずは、なぜ仕事をしない上司がいるのか、その理由を確認していきましょう。
役職を持った人に仕事をしない人がいる理由
前段で紹介をしたとおり、仕事をしない上司は実在します。部下にとっては扱いが難しい上に、評価査定にも関係してきます。仕事をしない、できないだけならまだしも、プライベートに入り込んで話をしてきたり、仕事の邪魔をしてきたりといったケースもあります。
いったいなぜ上司は仕事をしないのでしょうか?
役職を持った人に仕事をしない人がいる理由を見ていきたいと思います。
入社したタイミングが良かったから
仕事をしない上司の特徴には、単純に「入社時のタイミングが良かった」ことが考えられます。
1986年~1991年まで日本はバブルと呼ばれる期間でした。バブル景気と呼ばれる期間は、実際の価値以上の評価が株や土地、建物、絵画、宝石など資産価格が投機目的で上がり続けて、大きな評価額が発生しているように見える期間のことです。
バブルを経験した人の年代は2022年時点で53歳~58歳前後の人が年代として当てはまります。
組織でいえばまさに上司にあたる年代の方が多い年齢層ではないでしょうか? 当時はそこまで仕事ができなくても好景気の影響で仕事にあぶれる人は少なく、仕事の適正の有無によって昇進が阻まれることが少なかったのです。
年功序列で上がってきたから
近年は終身雇用制度の崩壊、メンバーシップ型からジョブ型雇用への移行が叫ばれていますが、従来の日本は終身雇用制度が主なスタイルでした。
終身雇用制度には「定着率の向上」「社員育成システムの確立」「人事評価制度のしやすさ」などがある一方で、「目的意識を持ちづらい」「年齢勤続年数に伴う賃金の上昇」などが挙げられます。
デメリットの部分は、まさに仕事をしない上司の特徴に当てはまる部分ではないでしょうか?
目立った成績を出さなくても、年功序列制度によりポジションや役職は上がっていき、そのまま管理職に就くというパターンです。実力やスキルがあるから役職に就いているわけではないため、能力的に不適格な管理職が発生してしまうのです。
年功序列で仕事をしてきた人の場合、「仕事をしない」のではなく「仕事ができない」ケースも考えられます。
新しいことについていくことが苦手だから
一般的に若年層に比べて、年齢を重ねるにつれて記憶の定着は落ちるとされています。
そのため、日々新しい技術が登場して変化の絶えない現代のスピードについていけない上司がいてもおかしくなく、それが原因で仕事をしなくなった人も一定数いるでしょう。
上司という立場上、新しい技術に慣れ親しんでいる若年層の部下に新しい技術や物事を聞くことができず、環境に取り残されてしまい仕事ができなくなっていく悪循環が生まれます。
年齢を重ねるとさまざまな経験が積み重なっていく反面、新しい仕事に挑戦する意欲や気力が衰えていきます。新しい環境への適応を拒んだり、リスクのある行動を避けたりする特徴も出てきます。
人間誰しも未知のことや経験のない物事に対して、「自分には無理」「自分ではできない」などメンタルブロックと呼ばれる否定的な思考を持ちやすいものです。
ただ立場が上の人間は、とりわけ「できないと思われるのが嫌だ」「失敗したら情けない」といったプライドによって新しいチャレンジに対してより抵抗を覚えるのです。
相対的な自己評価ができないから
相対的な自己評価ができなくなる人も多くなります。
仮にも会社という組織で役職に就いている上司は、多かれ少なかれ成功体験を持っています。その成功体験がプライドとなり、客観的な自己評価ができず、仕事をしなくなったことも考えられます。
「私が若い時は~」などが典型的な言葉になりますが、当時の成功体験が現代でそのまま通用するとも限りません。前述したように変化のスピードが早い現代では、むしろ当時の成功体験は邪魔になってしまうことも考えられます。
経験に基づいた成功のため、上司もある程度の自信を持って部下にアドバイスや指導を行いますが、まったく見当外れのアドバイスになってしまうケースも少なくありません。本人は仕事をしているつもりですが、部下からすると的外れの言動をしているだけの「仕事をしない上司」と映ってしまうのです。
仕事しない上司が発生するカラクリを知ろう
役職を持った人に仕事をしない人がいる理由を見てきましたが、仕事をしない上司が発生する要因はなんでしょうか?
「なんでこの人が上司なんだ?」と、ストレスが溜まっている人もいるかも知れませんが、仕事をしない上司が発生するカラクリを知れば、溜飲を下げることができるかもしれません。
実際に利益を上げているのは2割の社員!?パレートの法則
「パレートの法則」をご存知でしょうか? パレートの法則とは「全体の数値の8割は全体を構成する要素のうちの2割が生み出している」という経験則のことです。
多くの場合、上司の評価は、部署やチームの成績によって決まります。つまり、上司が仕事をしなかったとしても部署やチームの成績が上がっていれば、上司の評価は上がります。
パレートの法則に則って上記の現象を考えてみると、上司は必ずしも仕事ができる必要はないのがお分かりいただけるのではないでしょうか。
これが仕事をしない上司を発生させるカラクリの1つです。
昇進したことでスキルの上限に達した!?ピーターの法則
ピーターの法則とは「能力を有する人間は昇進することで能力を無能化していき、いずれ組織全体が無能な人材と化してしまう法則」のことです。
ピーターの法則は南カリフォルニア大学教授であったローレンス・J・ピーターとレイモンド・ハルによる『[新装版]ピーターの法則 「階層社会学」が暴く会社に無能があふれる理由』で提唱されているものです。
著書の中で「人は自己能力の限界まで出世をする」「無能な人はそのポジションに留まり、有能な人は限界まで出世するが、そのポジションで無能化する」とされています。
つまり、上司が仕事をしないのは「上司になることで無能化した」可能性があるということです。
多くの企業は階層ごとに評価されて昇進をしていき、現在就いている地位で有能と評価された人材は次の階層へ昇進していきます。しかし、昇進後の地位で必要な職務遂行能力がなかった場合、その人物はそれ以上昇格することがなく無能化して、その地位を維持します。
これにより組織で無能な管理職が発生していき、仕事をしない上司が増えていくのです。
仕事をしない上司と頑張って一緒に働くためのコツ
冒頭でも紹介をしたとおり、仕事をしない上司がいたとしても上司を変えることは難しく、その環境下で仕事をしていかなければならないことが多いでしょう。
上司に対してイライラや不満を持ち続けても、環境が変わらないのであれば「上司と頑張って一緒に働いていく」と視点を変えた方が有意義になります。
本項目では何もしない上司と一緒に働いていくためのコツを紹介します。
仕事をしてもらおうと期待しない
まず仕事をしない上司に仕事をしてもらおうと期待しないのが、一緒に働いていくためのいちばんのコツです。
他人への期待というのは、「こうあってほしい」「こうしてほしい」という願望に似た要素があります。その願望まで相手が達しないから、相手に対して腹が立ったりイライラしたりしてしまいます。
そのため、上司に対して仕事をしてもらおうと最初から期待をしないで、いないものと考えてしまうのも、上司と一緒に働いていくための方法です。
誤解のないように言っておくと、上司を無下に扱ったり無視したりするのではなく、期待をしないだけです。コミュニケーションや相手を敬う態度や姿勢はそのままです。あくまでも「期待をしない」だけです。
ほかの上司や同僚との連携を強める
それでも上司を変えようと働きかけたい方もいるかもしれません、その場合は1人で取り組まず、ほかの上司や同僚と連携するほうがよいでしょう。
たとえば、周囲に協力をしてもらい、仕事や商談の進め方などでの悩みや不明な点をあえて「仕事しない上司」にしてもらうなどです。
他人から頼られて嫌な気持ちになる人は少なく、期待に応えようとやる気を出してくれる場合があります。
上司の自尊心をうまく持ち上げて、上司自身が積極的に動きたくなるよう、周囲と連携をして行動してみましょう。
上司を操る「ボスマネジメント」をマスターしよう
「ボスマネジメント」とは、その名のとおり「ボス」を「マネジメント」する能力のことです。
一般的にマネジメントというと、上司から部下に行うイメージがありますが、ボスマネジメントは逆の部下から上司にマネジメントを行います。
戦略的に部下から上司にマネジメントを行うことで、より良い信頼関係の構築ができると共に仕事が進めやすくなる、実現したいことの支援を受けやすくなるメリットがあります。
マスターするために意識すること
ボスマネジメントをマスターするためには、「状況判断」「好みの把握」「報連相」「自己開示」「信頼と信用」などを強化していくことが必要です。
それぞれ解説していきます。
状況判断
ボスマネジメントは、上司に対して積極的に部下から働きかける必要がありますが、いくら仕事をしない上司とはいえ、業務や都合で手が離せないときもあるでしょう。
どのタイミングで働きかければ効果が最大化できるかの見極めは、ボスマネジメントを行う上でとても重要です。
好みの把握
人間関係を構築する際、相手が好む思考や行動パターンを知っておくと、より戦略的にボスマネジメントを実行できます。
たとえば、何らかの企画やアイデア出しを行う際は上司の好みや傾向を抑えておくと、採用率が上がるなど上司に対して好印象を残すことに繋がります。
報連相
ビジネスシーンで必須といえる報連相を徹底するのも、ボスマネジメントに必要な項目です。
報連相は「報告」「連絡」「相談」の略称で、報連相はどんなビジネスの場面でも大切になります。
報連相を行う際に注意をしたいのが、小さな約束をしっかり守るのが大切です。上司が知らないことがないよう、組織全体の成果を上げてもらうのはボスマネジメントの一環にもなります。
自己開示
自己開示をするのは人間関係構築の際の基本になるものです。
積極的に自己開示を行う部下は、上司にとってもかわいく感じられるもので、仕事だけでなく私生活などの相談も積極的にしてみるのもおすすめです。
信頼と信用
相手に動いてもらうには、まずは信頼と信用を積み重ねていきましょう。
信頼と信用を積み重ねるには、ここまで説明したことをしっかり実践していくのが大事です。
相手からの信頼を得るには、やはり自分からの自己開示が大切です。
まとめ
上司が仕事をしない理由や発生要因、上司へのイライラを解消させる方法などを解説してきました。
仕事をしない上司は理解しがたい存在だと思います。そんなときは相手からのアクションを待つのではなく、自分から積極的なボスマネジメントを実行しましょう。
その中でも大切な項目は自己開示です。自己開示はすべてのコミュニケーションで必須の項目のため、身に付けて損のない能力です。
仕事をしない上司にイライラしている人は、ぜひ本記事の内容を明日からの仕事に活かしてください。