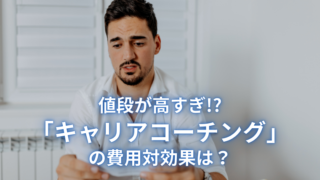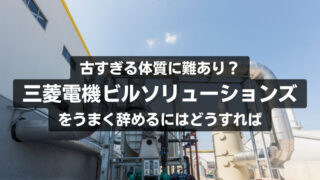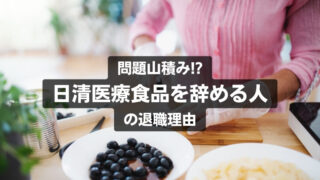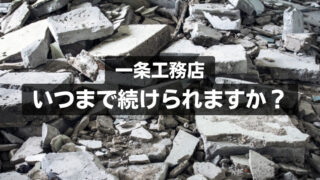転職活動を行う際に必要になるといわれている「自己分析」。
しかし自己分析を行う目的が曖昧なまま進めてしまう、あるいは分析が荒い人も多く見受けられます。
その結果「自己分析なんかしてもほとんど意味がなかった」「役に立たなかった」と感じてしまう人もいらっしゃいます。
しかし転職の際に自己分析を行うのは、単純に「内定を得られやすくなる」「面接の回答がスムーズになる」という理由だけではありません。
自己分析を通して、自分が転職に対して何を求めているのかクリアになるのがいちばん重要です。自分の軸を明確にすることで、単に「転職できる」だけではなく、将来的なキャリア戦略を立てることができるようになります。
この記事では、自己分析を行う理由を述べたうえで、具体的な自己分析のやり方を解説していきます。
キャリアアップの強力サポート!
「非公開求人」多数のエージェントにまずは登録
転職活動前に自己分析が必要な5つの理由
まず、自己分析が必要となる理由、自己分析を行う目的について整理して解説していきます。
自己分析を行うことで得られるメリットは主に次の5つです。
- 本当に転職すべきかどうかわかるようになる
- キャリア戦略を立てることができる
- 応募先の業界・職種を決めることができる
- 応募先の企業とのミスマッチを防ぐことができる
- 転職後に活躍しやすくなる
それぞれ補足解説していきます。
本当に転職すべきかどうかわかるようになる
なぜ、あなたは転職を検討しているのでしょうか。転職は、主に2つに分けることができます。
- 逃げの転職
- 攻めの転職
「逃げの転職」とは、現職に嫌なところ、不満点があり、そこから逃避するための消極的な転職を指します。この消極的な理由での転職はあまりおすすめできません。
もちろんいまの職場の環境が非常に悪く、心身の調子を崩すようであれば、そこから逃げるのは当たり前ですが、それでもポジティブな理由でもって転職(攻めの転職)をしたほうが、失敗するリスクを減らせるのです。
本当に転職が必要なのか、なぜ自分は転職すべきなのか、どのような企業に転職したいのか、自己分析を通して明確になります。
キャリア戦略を立てることができる
中長期的なキャリア戦略を立てられるようになることも、自己分析を行うことの大きなメリットです。
転職というのは「内定を得られるかどうか」だけではありません。内定を得て、承諾をして働きはじめてからのほうが本番です。
転職を決めたあとに自分はどのような仕事に携わり、将来的にどのようなポジションに立ちたいのか、自分の価値観を見つめなおすことで中長期的なキャリア戦略を立てることができます。
応募先の業界・職種を決めることができる
キャリア戦略にも関わることですが、自己分析を通して応募先企業の業界・職種を決めることができます。
自分が仕事に対してやりがいを感じている部分、得意とするところを見定めたうえで将来像を設計しましょう。
たとえ未経験であってもキャリアの大きな変化を起こしたいのか、それともこれまでの経験を活かした職場を選ぶのかは、自分の価値観を知らないと決めることができません。
応募先の企業とのミスマッチを防ぐことができる
自分が転職先に求めるもの、自分の価値観の軸がしっかりしていれば、応募先企業とのミスマッチも起こりにくくなります。
なんとなく「おもしろそうだから」「有名な企業だから」といったふんわりとした理由で転職を決めてしまうと、あとで「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
自己分析を行うことで「どのような企業に転職すべきか」明確になります。自分にマッチしていない企業に応募することもなくなり、転職活動も効率化できます。
転職後に活躍しやすくなる
転職の際に自己分析を行うべき理由の最後は「転職後に活躍できる」可能性を高めるためです。
「転職の失敗」というと「内定を得られなかった」「待遇が下がった」ということだと思いがちですが、違います。
「転職の失敗」とは内定を得られたものの、いざ働いてみると「自分の想像していた環境とは違っていた」「自分の得意を活かせる環境ではなかった」「仕事がやりにくくてストレスが溜まる」といった実際と期待値とのギャップに苦しむことです。
自分が何を望み、会社に何を求められているかをすりあわせておくことで、そのギャップを少なくすることができるでしょう。
ここまで転職の際に、自己分析をしておくことの目的と重要性を解説してきました。いよいよ、具体的にどのように自己分析をすればいいのか見ていきましょう。
転職のための自己分析のやり方1:キャリアの振り返りを行う

初めての就職ではなく、転職をする場合にまずしておきたいのは自身のキャリアを振り返ることです。
キャリアの振り返りのためには、エクセルか何かで簡単に「キャリア年表」をつくってみることをおすすめします。次の項目は必ず記載するようにしましょう。
- 自分の年齢
- キャリアのなかでの重要な出来事
- 得られた知見
- モチベーション曲線
その他「私生活の変化」「社会の出来事」もあわせて記載すると、どのような出来事が起き、自分の感情がどのように動いたのか思い出しやすくなります。
「出来事」「得られた知見」「モチベーション曲線」を記載するうえでのポイントを簡単に見ていきましょう。
出来事
出来事は「ご自身の客観的な立場での出来事」と「主観的に感じる成功・失敗事例」に分類されます。
客観的な立場の変化とは、たとえば「入社」「転職」「配属の決定」「部署異動」「昇格」「転勤」「出向」「退職/転職」などです。簡潔な仕事内容もあわせて記載しておくと、後々の職務経歴の洗い出しにも役立ちます。
一方「成功・失敗事例」は、主観的な物差しで記載して問題ありません。
- 部署間での連携不足のため、クライアントからのクレームが多発
- 既存の大口の取引先の事業撤退、新規顧客の獲得に奔走
- 会社の表彰式でMVPを獲得
など、大きな印象を受けた出来事を記載しておくと、自分が何を重要視しているのか理解することができます。
得られた知見
上のような「出来事」を受けて、自分は何を学んだのか、どのような成長があったのかあわせて記載しましょう。
- 自分が与えられた仕事の枠に閉じこもる傾向にあることに気づいた
- 円滑に仕事を進めるため、定期的なコミュニケーションを取る機会をつくるようにした
- 生産性を上げるためタイムマネジメントを取り入れた
- 人的なミスの発生を「仕組み化」「マニュアル化」で解決する発想を持ち、実行できるようになった
たとえ失敗があったとしても、そこから学んだこと、それを乗りこえた経験があるはずです。
自分の過去の経験を改めて意味づけして、どのように成長してきたのか振り返ってみることが重要です。
モチベーション曲線
良い時期もあれば、悪い時期もあったはず。
感情がプラスの方向に向いていたのか、それともマイナス方向に向いていたのか、時間の推移とともに、おおまかにメモしてみるといいでしょう。
「出来事」とあわせて見てみることで、自分の気持ちがどのようなときに前向きになるのか、逆にどのようなときにモチベーションが下がってしまうのか認識することができます。
キャリアの振り返りを行うことができたところで、次は「WILL」「CAN」「MUST」のフレームワークを使った自己分析に移りましょう。
このフレームワークを使うことで、転職を決める際の軸ができあがります。思いつきの転職で失敗しないためにも、ぜひ実践してみてください。
自己分析のやり方2:「WILL」「CAN」「MUST」のフレームワーク
念のため「WILL」「CAN」「MUST」のそれぞれの意味を、確認しておきましょう。
- WILL……何をしたいのか、どうなりたいのか
- CAN……何ができるのか、得意としているのか
- MUST……何をしなければならないのか
ご自身が「したいこと」「できること」、そして会社が求めているもの「MUST」が重なっている領域が広ければ、転職に満足する可能性が高くなります。

「自分のことなのだから「WILL」「CAN」はすでに知っているはずだ」と思うのは早計です。転職面接の際に、客観的に伝えられるようにするためにも、整理しておきましょう。
いちばん重要な「WILL」の見つけ方
転職の際には「何ができるのか」「どんな実績を積んできたか」が問われることが多いため「CAN」については深堀りする一方、WILLについては軽視する方が見られます。
ただ応募先の企業も、あなたが何をしたいのか、どんなキャリアを築きたいのか、その意欲の強さも含めて確認したいと考えています。
また自分が積極的に行いたいと思っていることではないと、なかなかモチベーションを高く維持したまま働くことはできません。
モチベーション高く働ける環境を得るためにも、しっかりとWILLを把握しておきましょう。
過去の経験から見つける
では、どのようにWILLを見つけていけばいいのでしょうか。
一つの方法として挙げられるのが、これまでの人生、これまでのキャリアでどのようなときに喜びを感じたか、先ほど紹介した「キャリア年表」とともに確認することです。
人が重要視する価値観にはさまざまなものがあります。「達成感」「協調」「成長」「承認」「貢献」「他者のバックアップ・育成」など、多様な価値観のなかでどれが自分にとって欠かせないものなのか、過去を振り返って確認しておきましょう。
現職の「不満な点」「満足している点」を5つずつ書き出す
いま会社に所属されている方であれば、現職の不満に感じている点、満足している点をリストアップしてみるのも有効です。
少なくとも、それぞれ5つ以上、ランキング形式で書き出してみることをおすすめします。
具体的にピンポイントで挙げると、よりWILLを掴みやすくなります。
たとえば「上司とソリが合わない」というのはやや抽象的です。「仕事を丸投げされるところ」「自分が出した成果を認めず、ほとんど評価されないところ」など、転職先ではそれを避けられる可能性が高いのか確認できるようなかたちにまで具体化しましょう(「上司とソリが合わない」だけでは、ほとんど運に左右されてしまいます)。
満足している点についても同様に具体的にリストアップしていきます。「人間関係が良い」「十分な裁量が与えられている」など書き出していくことで、自分が働きたい企業像が見えてくるはずです。
自分への質問から「軸」を見つける
自分の価値観を問う質問を繰り返すことも、仕事探しの軸を見つけることにつながります。
- いちばん楽しいと思えた瞬間はいつか
- 10年後何をしていたいか
- いちばん尊敬する上司は誰で、どんなところを尊敬していたか
- 仕事でいちばん嫌だった体験はなにか
- 何のために仕事をしているか
など、さまざまな角度から考えてみるとよいでしょう。
転職の最大の武器となる「CAN」の見つけ方
転職の最大の武器であり、他者と差別化できる要素となるのが「CAN」です。
自分ができることを十分に理解したうえで、他者にも伝えられるようにしておきましょう。
経験・スキルの棚卸しを行う
すでにキャリアの振り返りを行っていれば、経験・スキルの棚卸しはスムーズにできるはずです。
どんな小さな経験、補助的な業務だったとしてもまずはリストアップしてみることをおすすめします。スキルに関しては資格取得などもしていれば、メモしておくこと。
出した実績については数字で示し、またそれがその実績がどのような行動・自分のスキルから出したのかまで分解してみましょう。自分の経験・スキルが再現性があるもの、他社でも活かせるものだと納得できるはずです。
自分の強み・得意・特徴を書き出す
経験・スキル以外にも、あなたの得意なところ、ポジティブな特徴、強みはあるはずです。
- 柔軟性がある
- 人間関係をうまく構築することができる
- 発想力が豊かである
などです。
さらにこのような特徴から、どのように仕事にプラスをもたらしたのか具体例を挙げられると最高です。
他人にヒアリングする
CANを見つけるうえで、他人にヒアリングしてみることも非常に有効です。
人は意外に自分の強みについて気づいていません。「得意なこと」「強みがあること」は、本人にとってはある意味で当たり前にできてしまうことなので、特に意識していないのです。
自分では「普通」と思っているのに褒められるところはないか、また改めて周囲の人に自分の強みを聞いてみると、新しいCANの発見があるかもしれません。
応募先企業と自分のすりあわせに必要な「MUST」の見つけ方
最後は「MUST」、必須条件となります。
志望先企業が何を「必須条件」としているのか確認するのは当たり前ですが、自分が転職先に希望する「必須条件」もしっかり把握しておいてください。
志望企業のMUSTを調査する
志望先の企業がすでに複数あるようでしたら、企業がどのようなMUSTを設定しているか確認しましょう。
求人を出しているのであれば、一般的には「必須条件」が書かれているはずです。自分にはその条件にあてはまっているか確認していきましょう。
ただその「必須条件」に業務内容、求められるスキルについて書かれていても、企業によっては暗黙的に他の条件が存在する場合もあります。たとえば「人物像」「転勤の可否」などです。
明示的に書かれていない部分については、志望する企業の公式サイトを読む、もし会社や代表取締役を取り上げたメディア記事があれば、それも探してチェックしましょう。かなりの程度、会社が求めている人物像をつかむことができます。
自分のMUSTを設定する
最後は自分自身のMUSTを設定しましょう。転職するにあたって考えるべき項目はいくつもあります。
- 給与・待遇
- 勤務地
- 休日・休暇
- 職場環境
- 社風
- 勤務形態
条件を絞れば絞るほど、候補となる会社は少なくなります。
なので、どこまでは譲れて、どこまでは譲れないのか線引きして、応募先企業を選ぶようにしてください。
ここまで書いてきたような自己分析を行っていれば、それほど悩むことはなく決められるようになっているでしょう。
まとめ
そもそも転職活動を行う前にやっておきたい自己分析の具体的なやり方と注意点を解説しました。
ほとんどの人にとって「ただ転職ができればいい」というわけではなく、「より自分らしく働きたい」「希望を叶えたい」という気持ちがあって、転職を決断するものと思います。
ぜひここで採り上げた自己分析を通して、理想の転職を実現させてください。
キャリアアップの強力サポート!
「非公開求人」多数のエージェントにまずは登録